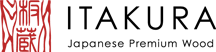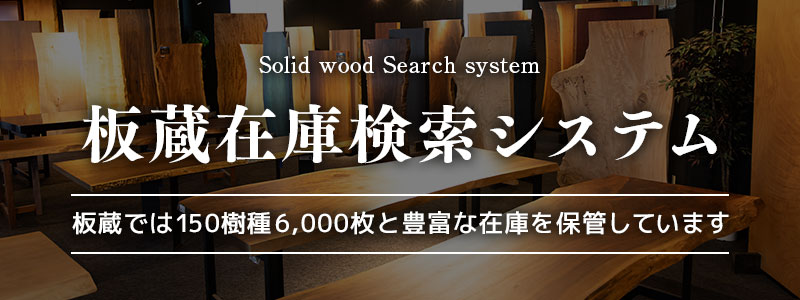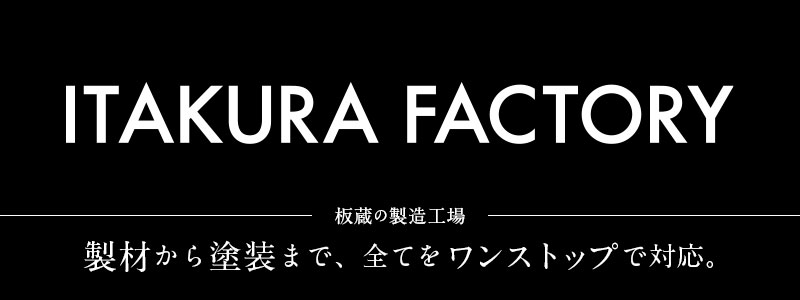こんにちは。
今日は一枚板に関わる専門用語をまとめてみました。
すでにご紹介したことのある言葉から、まだ紹介していない言葉まで、写真付きでご紹介したいと思います。
下記は用語の五十音順に並んでおります。
〇浮造り(うづくり)

こちらは針葉樹、特にスギによく見られる加工の一つです。
木が成長する段階で春から夏に成長した部分は柔らかく、秋から冬の部分は硬くなっているため、加工すると柔らかい所が削れ木目が浮いているように見えることから、『浮造り』といいます。
〇原板(げんいた)

丸太から板にひいたそのままの状態を原板といいます。
その後加工を経れば基本的に原板と呼ばれることはありません。
〇木口 (こぐち)

立ち木の状態で切断された面を木口と呼びます。
年輪を数えるときは木口を見れば把握することができます。
〇末 (すえ)

立ち木の状態で上に伸びていく方を一枚板にした時『末』と呼びます。
一般的には末の方が長さが短くなります。
また、立ち木の状態で上に伸びる最先端の部分を「梢(こずえ)」といいます。
〇接ぎ (つぎ)

一枚板は一本の木から切り出した一枚ものですが、接ぎとは一枚ではなく二枚・三枚と継ぎ足してあるもののことを言います。
また、一般的に言われる集成材とは違います。
〇共木 (ともぎ)

同じ一本の丸太からとれた数枚の板のことを共木と呼びます。
同じ丸太のため色や木目が似ていて、接いだり空間を統一したい場合に共木で合わせることがあります。
〇節 (ふし)

節は枝が木部に取り込まれたときにできるもので、一般的にはこの節がない材の方が価値があります。
これは一枚板に限らず、木材では一般的に節がない方が価値があるとされています。
〇耳 (みみ)

一枚板の特徴ともいえる耳と呼ばれる部分は、丸太時の樹皮と呼ばれる一番外側、手で触れることのできる部分です。
樹皮は当然とりますが、木は丸くなっています。
その部分を耳と呼びます。
〇無地 (むじ)

節がない状態の一枚板のことをいいます。
また、節がなく杢もない時にも使われます。
〇木目 (もくめ)

一般的には表面に見られる年輪を指しています。
〇杢 (もく)

立ち木の状態での環境が関わっているとされ、病気や強い圧迫を受けるなどした場合、杢と呼ばれるものが出る場合があります。
一概にはいえず、出やすい樹種等もありますが、価値が高まることは間違いありません。
〇元 (もと)

末と対になる言葉で、立ち木の状態で地面に近い方を『元』と呼びます。
一般的には元の方が幅が広くなりますが、例外は当然あります。
他にもなにかわからない様な専門用語があれば、お問い合わせください。
分かる範囲でお答えさせて頂きたいと思います!